月刊ほんナビ 2025年3月号
📕 「星をめぐる人々と文化」
紹介:原智子(星ナビ2025年3月号掲載)
今シーズンの星空は、明るい冬の星座に木星と火星が加わりいっそうにぎやかだ。星座にまつわる物語は世界各地にあるが、やはりスタンダードなのはギリシア神話を基にしたものだろう。『星のギリシア神話研究』は、『星ナビ』2018年5月号から早水勉氏が不定期で連載し2025年4月号で最終回を迎える「エーゲ海の風」と、2022年6月号「星座制定100周年」特集で掲載した特別編をまとめたムック。筆者も同コーナーのファンで掲載されるたびに興味深く読んできたが、それをこの一冊でいつでも読み返すことができるのはありがたい。しかも、貴重な資料や写真をオールカラーで見ることができるなんて感激だ。今までなんとなく聞いていたギリシア神話を文化・天文学・古代史の観点から詳しく学ぶことで、物語の生まれた背景を知り、神々や英雄たちについて深く理解することができる。
そんなギリシア神話を交えながら、星座や天体についてわかりやすく教えてくれる場所がプラネタリウムだ。『星座と星めぐり』は「コスモプラネタリウム渋谷」の解説員8人による、星空とプラネタリウムを紹介する読み物。同館は、かつて渋谷にあった五島プラネタリウムで解説をしていた永田美絵さんや村松修さんも所属する施設。最新の設備を備えつつ解説員の語りで星空を案内するという、ぬくもりを感じる投影を続けている。この本でも個性的な8人が順番に、季節の星座や天体について話しかけるように教えてくれる。さらに、来館者に合わせて暗闇で解説する難しさや、失敗などの裏話も。さっそく「読みたい!」と思ったあなた、せっかくなら同館で実際に解説を聞いて購入するともっと楽しめるだろう。
星にまつわる文化は、もちろん日本にもある。『星占い星祭り(新装版)』は、古代中国伝来の天文道・陰陽道・道教・密教の思想や信仰をもとにして、日本で独自に展開した「星占い」や「星祭り」を解説した史書。2024年の大河ドラマ『光る君へ』でも安倍晴明が登場するなど、「星の動き」が政治や人々の生活に大きな影響を与えていたことがわかる。同書はもともと、江戸・明治期の民俗や風俗に関する書物を扱っていた青蛙房が1974年に刊行し、2016年に新装版を出版した。同社が2019年末に閉業すると、2024年に吉川弘文館が復刊させた。名著を眠らせず、世に送り出してくれたのは素晴らしい。
同じく、装い新たになったのが『天文学者たちの江戸時代(増補新版)』。2016年に新書判で出版されたものが、このたび文庫で登場。江戸時代に中国や西洋の知識を取り込み、自身の知恵で開拓していった渋川春海、麻田剛立、間重富らの姿がよくわかる。新たに、補章「書物と西洋天文学」と渡部潤一氏の解説「宇宙への情熱 ― 時代を超えても変わらぬ思い」が加わった。2025年の大河ドラマ『べらぼう』は多数の作家と作品を世に送り出した人物の物語だが、この本からも江戸時代に活躍した人々の苦悩と情熱が伝わる。
ところで、先日、渡部潤一さん夫婦と筆者夫婦の4人でタクシーに乗る機会があった。乗車時間が長めだったので、この4人が参加した観測チームによる海外遠征の思い出話で盛り上がった。これを聞いていた運転手は「この客たちは何か珍しいものを見てきたようだ」と思ったことだろう。『タクシードライバーとの宇宙談義』は、アメリカ人宇宙生物学者がタクシードライバーとの会話にインスピレーションを得てつづった科学エッセイ。運転手の質問「宇宙にタクシードライバーはいるのかな?」は、素朴でありながら実に核心をついた疑問だ。地球外生命や火星移住、宇宙探査の意義など、専門家が解説する話をタクシードライバーになった気分で読もう。
最後に紹介する『宇宙の一瞬をともに生きて』は千葉景子氏の自伝。弁護士で民主党政権時代に法務大臣を務めた彼女の趣味は天文で、『星ナビ』にも登場している。小学生のときから五島プラネタリウムに通い、閉館後に発足した「渋谷星の会」では名誉会長を務めている。彼女の言葉「宇宙の時間では人間の一生は一瞬だ。なのになぜ人は争うのだろう」は、星空を愛する多くの人が思う気持ちでもある。夜空に光るものが、ミサイルではなく星や月であってほしい。
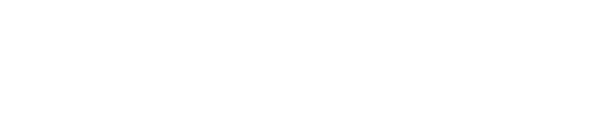
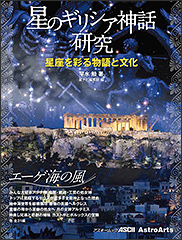
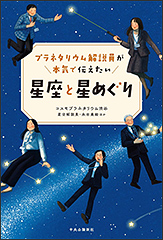
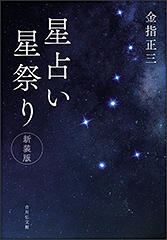

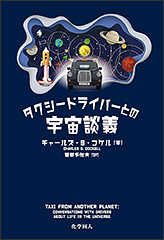














![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)