月刊ほんナビ 2025年4月号
📕 「ドラマチックな夜空に出会う」
紹介:原智子(星ナビ2025年4月号掲載)
「百聞は一見にしかず」というように、どれほど言葉を尽くしても一枚の写真にかなわないことがある。「奇妙な形の岩山」とか「七色のオーロラ」とか言われるよりも、この本の1ページを示される方が、圧倒的な迫力に目を奪われる。『絶景の夜空と地球』は希有な風景と神秘的な夜空を切り取った写真集。前景にあるのは、山や奇岩、湖や川、建物や樹木、天文台の施設やパラボラアンテナ。そして、後景に広がるのは、満天の星や天の川、極地に輝くオーロラ。光学専門の物理学者でもあるカメラマンと、宇宙論を専門とする科学ジャーナリストによって語られる170枚からは、地上と天上で起こるスペクタクルなドラマを感じる。
ドラマチックな光景は、限られた場所だけで起きるわけではない。私たちの日常生活でも、美しい雲や月や星を見ることができる。『やさしい空と宇宙のはなし』は、気象分野の専門家である武田康男氏と天文学者の縣秀彦氏が互いの知識や意見を交換しながら「空と宇宙」について教えてくれる解説書。地表近くで見られる虹やグリーンフラッシュなどの光学現象、対流圏で起こる雲や雨などの気象現象、その上で起こるオーロラや流星などの発光現象、日食や月食などの天文現象など、広く「空」で起こることをわかりやすく(易しく)親しみやすく(優しく)語る。最終章では、空と宇宙に興味を持った読者(若者)たちへ進路や研究について、二人の「先生」がエールを送る。空への好奇心をかき立ててくれる一冊。
ドラマチックな空を描いた画家の一人にゴッホがいる。筆者もオルセー美術館で『ローヌ川の星月夜』を見たとき、「この星の並びは北斗七星だ」と思った。『ゴッホは星空に何を見たか』では、『夜のカフェテラス』や『星月夜』などの作品に描かれた夜空について、天文学の見地から多角的に検証している。さらに、宮沢賢治について造詣が深い谷口義明氏らしく、賢治とゴッホの共通点を探ることで彼が描きたかった神髄に迫る。
当誌先月号(2025年3月号)から瀬名秀明氏の小説「オリオンと猫 野尻抱影と大佛次郎物語」の連載が始まった。『三つ星の頃』は、野尻抱影が編集責任を務めていた雑誌『中学生』に載せた小説から選りすぐりの11編をまとめ、1924(大正13)年に発刊した唯一の短編集。生誕140周年を記念して今年、復刊された。表題作の「三つ星の頃」のように、オリオン座を見たときに忘れがたい思い出が浮かぶ人は多いだろう。
次の小説も、夜空に青春が重なる物語。『君と、あの星空をもう一度』は「幼なじみと見たスピカ食を10年後の2024年にもう一度」と願う高校生たちの話。宇宙で起きる奇跡的な瞬間を、誰かと一緒に見られるのはうれしいこと。それを再度、同じ相手と同じ感動を味わえたら幸せだろう。若い読者はキュンとして、ベテラン天文ファンにはエモいかも(本誌p56より関連記事)。
さて、ここまで夜空にまつわるドラマを紹介してきたが、実際に星空を見るときに役立つガイドブックを2冊。『まんがで覚える 星座・星名と神話がわかる本』は全編ふりがなつきで、星座について楽しく学べる児童書。漫画や「こぼれ話」で神話を読んだら、「星座のさがしかた」を参考にして実際の夜空で星をたどろう。
本格的な天体観測をする人には『星雲・星団・銀河ビジュアル図鑑』を。望遠鏡で星雲星団、銀河などを観測するのに必要な星図とデータが網羅されている。あわせて、参考になる天体写真や撮影ポイントも紹介されているので「これから望遠鏡を使った撮影にチャレンジしたい」というビギナーにとって心強い。春になり多くの銀河が見られるようになったら、この本を片手に片っ端から望遠鏡に入れて観察や撮影をするのはいかが。自分だけのドラマに出会えるかもしれない。
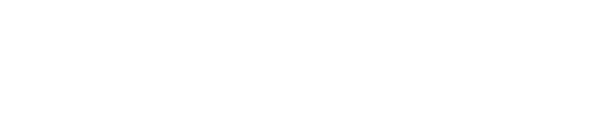
![『[フォトミュージアム] 絶景の夜空と地球 景観遺産と天体撮影のドラマ』(Amazon)](image/250401.jpg)
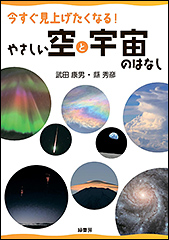

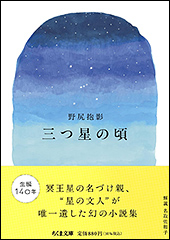
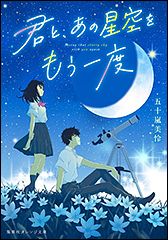
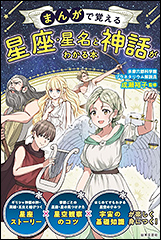














![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)